コラム
労働裁判の判例
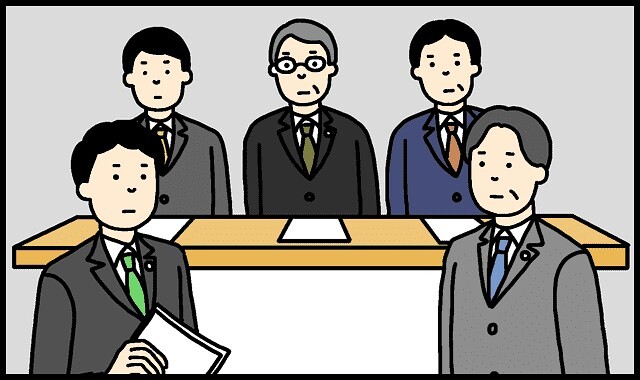
今回は、「労働裁判の判例」について
ご紹介いたします。
1.労働判例の基本
裁判所が下した判決を、一般的に「判例」と
いいます。
但し、最高裁判所の判決だけを「判例」、
下級審の判決を「裁判例」と呼んで区別する
こともあります。
裁判における主張や判決は、最高裁判決を
踏まえて行われるため、裁判を想定した
実務では十分に意識する必要があります。
特に労働問題では、労働基準法や労働契約法の
条文内容だけでは判断できない部分が多く、
「判例法理」(判例の蓄積により形成された
考え方)が重要となります。
最近はインターネットにより、判例情報の
入手が容易になり、事前知識をインプット
できる環境が整ってきました。
突然発生する労務トラブルへの対応にも
関連する判例を知ることで、理解が進み、
やるべきことが明確になるというものです。
そこで、今回は最新の重要労働判例を紹介
したいと思います。
2.就労の意思の喪失時期[フィリップス・ジャパン事件]
【概要】
能力不足で解雇された従業員が、退職勧奨等を
行った上司に対して不法行為に基づく損害賠償を、
会社に対しては、解雇後の賃金と使用者責任に
基づく損害賠償を、請求した事件です。
上記従業員は解雇後に他社に転職しており、
解雇後の就労意思の喪失時期が争点となりました。
【事実】
A氏はX社にパラリーガルとして就職した後に
司法試験に合格しました。
司法修習のために休職し、その後、育児休業を
経て復職しましたが、弁護士としての能力不足を
理由に退職勧奨を受けました。
退職勧奨に応じなかったA氏はX社から解雇され、
別会社(Y社)に入社しましたが、X社に対して
解雇の無効を提起しました。
一方、X社は、裁判提起後に上記解雇を撤回し、
A氏に復職を求めるとともに、上記裁判において
A氏がY社に就職した時点で、X社への就労意思を
喪失していると主張したのです。
原審(一審)は、X社の上記主張を認めず、
A氏が自認した日をもって、就労意思の喪失と
黙示の退職合意が成立する、としました。
他方、A氏が主張したX社の不法行為と使用者
責任も否定され、A氏とX社の双方が控訴しました。
【控訴審判旨】原判決を一部変更
➀Y社での試用期間中に解雇予告等はなく、
職務能力がないことを理由に、後に解雇される
惧れが相当低下している。
②Y社の雇用条件は、賃金の面でX社より明らかに
好待遇であり、第2子出産のために産前産後
休業や育児休業も取得できた。
③X社では弁護士としての能力を欠いていると
評価され、解雇までされた。
これらの事情が考慮され、「Y社での試用期間が
終了した時点で、A氏があえてY社を退職してまで
X社で就労する意思があったとは認められない」
「Y社の試用期間が終了した時点において
X社への退職合意が成立したというべきである」
という判決がなされました。
本控訴審の高裁判決では、原審の判断を変更し、
「就労の意思」の喪失時期を早め、Y社における
試用期間終了日としました。
解雇紛争が、転職によって、早期解決に繋がる
ケースもあり、就労意思の判断をはじめとして、
解雇後の転職状況が重要な鍵となりそうです。
3.手当廃止(不利益変更)の有効性[国立精神・神経医療研究センター事件]
【概要】
就業規則の不利益変更の有効性の判断については
労働契約法9・10条にて規定されていますが、
実際の裁判では諸々の事情が考慮されることから、
結論の予測は決して容易ではありません。
そのため、経過措置や調整給等の不利益緩和
措置を設けることで紛争リスクを軽減させる
こともあります。
本事件でも、手当の段階的削減という経過措置が
設けられていました。
【事実】
B氏が経営する病院では、特定の病棟に勤務する
従業員に対して特殊手当を支給していましたが、
2018年4月から年20%ずつ段階的に減額し、
2021年度で完全に廃止する給与規定の変更
(以下「本件変更」)がなされました。
同病院で勤務する看護師・保育士ら(C氏ら)は、
本件変更は無効であるとして、廃止前の特殊業務
手当の支払いを求めました。
原審は、本件変更を合理的であると判断し、
C氏らの請求を棄却したため、C氏らは控訴
しました。
【控訴審判旨】原判決変更・C氏らの請求認容。
➀地域手当が引き上げられていましたが、
人事院の勧告を受けて実行されたもので、
特殊業務手当の代償措置とは評価できない。
②夜間看護手当が増額されましたが、特殊業務
手当と支給対象者が異なっているほか、
増額の目的が『人材確保等』である。
③役職手当の増額についても、特殊業務手当の
受給者とは対象者が異なっているうえに、
増額の目的は『他職種の役職手当との均衡、
職責の増大等の考慮』である。
④本件組合とB氏との交渉期間が僅か1ヶ月半
しかなかった。
尚、本件特殊業務手当の廃止変更は、5年間
かけて段階的に廃止するという経過措置が
設けられていたものの、①~④の事由を踏まえ、
「それらが代償措置に該当しないことから、
本件特殊業務手当の廃止変更が、労働契約法
10条にいう合理的なものとは認められない」
という判決になりました。
B氏は、組合との間で5回にわたる団体交渉
を行い、他の待遇アップも実施しましたが、
高裁判決は交渉を不十分と評価し、他の待遇
アップも代償措置とは認めず、原審の判断を
覆し、特殊業務手当の廃止を無効としたのです。
例え、経過措置を設けていても、他の事情から
不利益変更の合理性が否定されることがある
ということです。
