コラム
巡回指導対策 適性診断の違反について
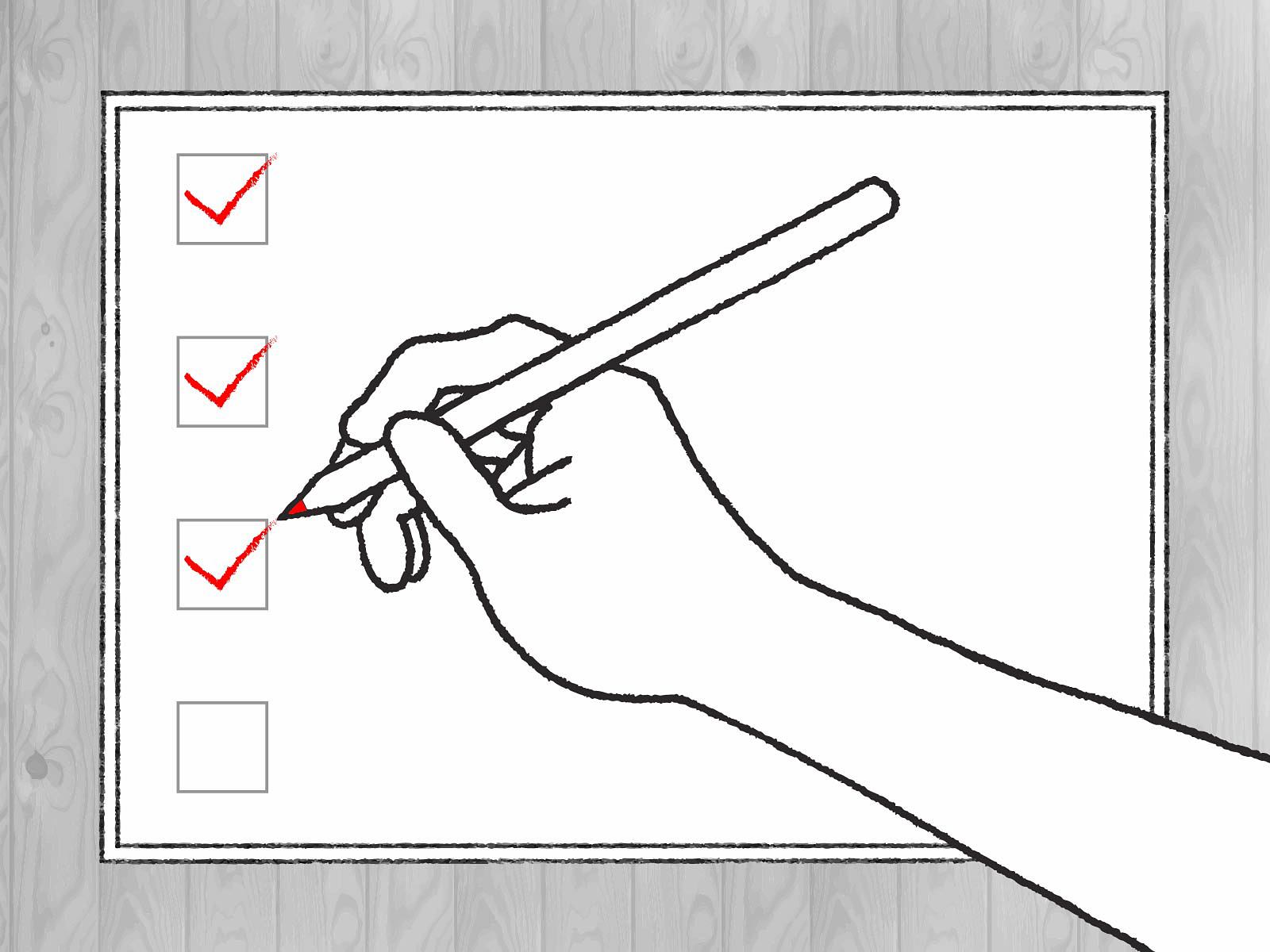
巡回指導の指導員が確認するポイントについて
令和2年7月15日に近畿運輸局から公表された令和元年度自動車運送事業者に対する監査と処分結果の中で、行政処分にかかる主な違反内容として2番目に多いのが教育等の違反(121件)ですが、その内67件が適性診断の違反です。
今回は、適性診断についてお伝えいたします。
運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を運転者に受診させることが義務付けられています。
安全確保のため、国土交通大臣が認定する「運転者適性診断」を受けなければならないのです。
運転者の診断を徹底して励行させるとともに、診断結果を日々の指導や教育時などに活用するとともに、運転者には結果を真摯に受け止め、自覚させることが大切となります。
日頃、安全運転を心がけていたとしても実際に自分がどんな運転をしているのか気づくのは、なかなか難しいものです。
運転の癖を科学的に測定し、安全運転につなげていくのが運転者適性診断です。
それぞれ顔が違うように、運転においてもそれぞれ個性を持っています。
まずは自分ではなかなか気づくことができない運転の癖というものを検査で測定します。
測定結果に基づき、それに対応する安全運転のアドバイスを行い、自身を知ること。
そして、それをその後の運転に活かしてもらうというのが運転者適性診断の目的です。
義務付けられている
適性診断の種類と対象は以下の通りです。
① 初任診断 新たに採用された者
② 適齢診断 65歳以上の者
③ 特定診断Ⅰ 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者。軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者
④ 特定診断Ⅱ 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者
なお、それぞれのケースの受診のタイミングは以下の通りです
初任運転者(上記①のケース)
当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に初任診断を受診させること。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させること。
なお、当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断を受診したことがある者は受診する必要はありません。
高齢運転者(上記②のケース)
65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。
事故惹起運転者 (上記③④のケース)
当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に受診させること。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させること。
なお、義務付けられている適性診断が未受診となっている場合の罰則(車両停止処分)は次の通りです。
受診なし1名 警告 (再違反の場合は10日車)
受診なし2名以上 10日車 (再違反の場合は20日車)
適性診断は時間はおよそ80~90分ほどかかります。
画面と音声の指示に従って全ての項目を順に行っていきます。
診断は優劣をつけるものではありません。
ドライバーの性格から安全運転態度、認知・処理機能、視覚機能まで多岐に渡り心理・生理面を科学的にとらえる診断内容になっています。
運転者適性診断の結果は、それぞれの運転者の適性に応じたものとなるため、それぞれの運転者が配慮すべき事項はさまざまとなります。
診断結果を活かして、自分のくせを理解・克服するよう、指導・監督を行っていくことが必要です。
適性診断の結果から、自分自身では気づきづらい、“運転のくせ”を知ることができます。
しかし、自分で自分のくせを克服することは、大変難しいものです。
そこで、適性診断結果の活用においては、運転者の指導教育を担当する管理者が「自分の運転の悪いクセを克服しようとする運転者を援助する」ことが大切です。
特に、面接による助言・指導を行う場合には、受診者に適性診断結果と今後の安全運転のためのアドバイスがうまく伝わるように、助言・指導を担当する管理者の心構えも重要です。
運転者は、自分のもつ事故につながりやすい特性が運転行動に現れないように、努力をして安全運転しているかもしれません。
管理者は、まず運転者のこの努力を認める、よいところは褒めて伸ばす、というような、運転者の現在の状態を受容することが大切です。
管理者等が安全運転のための助言・指導を行うためには、適性診断結果の見方を正しく理解しておく必要があります。
また、適性診断票には、測定結果に基づく安全運転のためのアドバイスも記載されているので、助言・指導を行うに際して、これらの情報をぜひ活用することが肝心です。
なお、自動車事故対策センターで受診した場合、受診した本人宛の適性診断票と、自動車運送事業者や指導する運行管理者が見てわかりやすいような指導要領がついた診断票の2つが提供されます。
これら2つの受診票により、ドライバー自身が安全行動の実践に取り組むだけではなく、見守る自動車運送事業者や指導する運行管理者が活用できるようになっています。
私は、お客様の巡回指導前に内部監査を行うことがよくあります。
その際に、適性診断を受診しているのですが、
活用しないままになっているケース
が多く見受けられます。
受診すれば義務は果たしたことになるのですが、時間と労力を使って行った診断の機会を
事故防止に活用しないともったいない
と思うのです。
適性診断は、監理者が主観で指導するのとは違い、客観的な診断結果です。
その分、本人としては、結果を素直に受け止めることが多いと思います。
素直になったときが、指導のチャンスでもありますから、診断のタイミングで指導を行うことをお勧めします。
なお、適性診断などをはじめとした各種講習を実施している専門機関は自動車事故対策センターだけではなく、民間の機関もたくさんあります。
適性診断を実施している機関はこちら→
一般診断は義務付けられているわけではありませんが、できれば、3年に1回受診し、指導の機会とすることをお勧めします
