コラム
年金制度改革
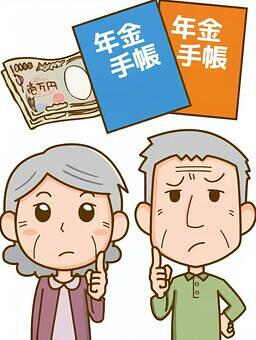
今回は「年金制度改革」についてご紹介いたします。
1.制度の見直し案
厚生労働省は、次期年金制度改正に向け、
令和7年通常国会への法案提出を目的に
制度見直し案を示しました。
令和6年末までに、社会保障審議会・年金
部会にて取り纏められている主な内容に
ついてご紹介します。
2.被用者の適用拡大
勤務先の企業規模や業種によって被用者
保険の適用の有無が変わるのは不合理だと
して、特定適用事業所の企業規模要件を
撤廃するとしています。
特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、
適用事業所の厚生年金保険の被保険者
(短時間労働者は含まず、共済組合員を含む)
の総数が51人以上となることが見込まれる
企業等と定義されており、昨年10月に
101人以上から51人以上に対象が拡大
されたばかりで、早くも、その51人以上
という枠すら撤廃しようというのです。
(結局2035年に先延べとなりました。)
更に、常時5人以上の従業員を使用する
個人事業所における非適用業種の運用が
解消され、全ての業種を強制適用にする
としています。
ちなみに、農業、林業、漁業、飲食店や
理容店などのサービス業、神社などが
非適用業種とされています。
尚、賃金要件(月額8万8千円以上)は、
最低賃金の上昇などを踏まえて引き続き検討
され、労働時間要件(週所定20時間以上)や
学生除外要件については維持される見通しです。
3.「年収の壁」への対応
被用者保険の保険料負担は、労使で
折半することが原則となっていますが、
健康保険に関しては、現行制度でも、
健康保険組合の特例として健康保険料
の負担割合を被保険者の利益になるよう
変更できるとされています。
今回の厚労省案では、この特例を参考に、
厚生年金にも特例を設け、労使の合意のもと、
被保険者の負担割合を引き下げることが
できるようにするとしています。
つまり、新たな適用に伴い保険料が
発生しても、事業主が負担割合を増やし、
被保険者の負担割合を軽減することで、
被保険者の手取り収入の減少や、就業調整を
回避しようというのが、この特例のねらいです。
また、保険料の総額が変わらないので、
将来の給付金額に影響が出ないのも特徴と
言えます。
只、今後、新たに対象となる50人以下の
企業に、従業員の負担割合を軽減するだけの
余裕があるか否かは不透明なところで、
殆ど実施されることのない特例となる懸念も
ありそうです。
4.標準報酬月額の上限引き上げ等
厚生年金の標準報酬月額は32等級に
区分されており、上限が65万円に設定
されています。
令和6年6月時点、その上限該当者は
278万人であり、被保険者全体の
6.5%を占め、男性に限れば243万人
(同9.6%)と等級別の最頻値となって
いました。
上限の見直し案は、75万円、79万円、
83万円、98万円の4案が示されており、
上限の引き上げは、対象者の保険料の
負担増加につながると同時に、将来世代の
年金給付水準の上昇が見込まれ、影響率は
それぞれ、+0.2%、+0.3%、
+0.4%、+0.5%と試算されています。
(現状、68万円、71万円、75万円の
3段階に変更されています。)
ほかにも、高齢者の活躍を後押しし、
働き方を公平な仕組みとする観点から
在職老齢年金制度の撤廃や緩和が検討
されています。
具体的には、現行の50万円に設定された上限
(上限以上の賃金を得ている60歳以上の
老齢厚生年金受給者を対象に、当該老齢厚生
年金の一部又は全部の支給を停止する仕組み)を、
62万円、71万円へ緩和する、或いは、
撤廃する、の3案です。
更に、離婚時の年金分割の請求期限を2年
以内から5年以内に延長する案等も出されて
います。
民法の離婚時の財産分与請求権の除斥期間が
2年から5年に改正されたことが要因のようです。
5.最後に
一見、労働者の方にとって働きやすい環境
づくりを目的とした合理的な年金制度改正の
ようですが、改正内容によっては、事業主の
負担増や、労働者の足かせになるものもあり、
諸手を上げて賛成というわけにはいかない
かもしれません。
そうした点を踏まえ、今後の年金制度の改正に
ご注目下さい。
